相続が発生した際、被相続人(故人)の銀行口座は自動的に凍結されます。
これは、遺産の不正使用を防ぐための重要な措置ですが、遺産分割や葬儀費用の支払いに影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、銀行口座の凍結が行われる理由から、その解除方法、対策まで詳しく解説します。
銀行口座の凍結とは?
銀行口座の凍結とは、口座名義人の死亡が確認された際に、金融機関がその口座の出金・振込を停止する措置です。
これにより、亡くなられた方の預金は相続手続きが完了するまで動かせなくなります。
凍結される口座には、普通預金、定期預金、証券口座、投資信託口座などが含まれます。
特に注意すべきは、故人の名義のすべての口座が対象となるため、日常的に使用していた口座であっても同様に凍結される点です。
口座凍結の理由
銀行口座が凍結される理由は、以下の3つに集約されます。
1. 遺産の保全
亡くなられた方の資産が不正に引き出されるのを防ぐためです。
死亡後も口座が自由に使用できる場合、不正な引き出しや資産の隠匿が起こる可能性があります。
2. 相続人間の公平性の確保
相続財産はすべての法定相続人で分割されるべきものです。
特定の相続人が勝手に資金を引き出すと、不公平が生じるため、口座凍結により一時的にすべての資産を凍結し、公平性を保ちます。
3. 法的手続きの円滑化
相続税申告や遺産分割協議をスムーズに進めるためです。
凍結により、正確な財産把握が可能となり、税務申告や分割協議が適切に行われるようになります。
口座凍結のタイミングと手続き
銀行口座が凍結されるタイミングは、以下のいずれかの状況で発生します。
- 金融機関への死亡報告:相続人や遺族が死亡届、戸籍謄本を提出した場合
- 公的機関からの通知:住民票の異動や死亡診断書の提出に基づき通知される場合
これにより、銀行は即座に口座凍結を行い、資金移動が停止されます。
銀行口座凍結の影響
口座凍結が行われると、以下のような影響があります。
1. 出金・振込の停止
故人の口座からの現金引き出しや振込が一切できなくなります。これにより、生活費や医療費の支払いに支障をきたす場合があります。
2. 自動引き落としの停止
公共料金、住宅ローン、クレジットカードの引き落としも停止されます。これにより、未納扱いとなり、延滞金が発生する場合もあります。
3. 遺族の生活資金の不足
特に故人の口座から生活費を賄っていた場合、急な資金不足が発生する可能性があります。
口座凍結の解除手続き
口座の凍結を解除するためには、以下の手順を踏む必要があります。
【1】相続人の確定
法定相続人を特定するために、戸籍謄本や除籍謄本を取得します。
【2】必要書類の準備
銀行によって必要書類は若干異なりますが、一般的に以下のものが求められます。
- 故人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 印鑑証明書
【3】金融機関への手続き
必要書類をそろえたら、銀行の窓口に提出し、相続手続きを進めます。
【4】資産の分配
相続手続きが完了した後、口座の資金が解除され、相続人間で分配されます。
口座凍結を回避・対策する方法
相続発生時に口座凍結の影響を受けにくくするために、以下の対策を事前に講じることが有効です。
1. 生前贈与
生前に一定額の資金を相続人に贈与することで、死亡後の資金凍結リスクを回避できます。
2. 共同名義口座の活用
信頼できる家族と共同名義の口座を作成することで、死亡後も引き出しが可能です。
3. 信託の活用
家族信託などを利用して、死亡後も資産を管理できるようにしておくことも効果的です。
まとめ
銀行口座の凍結は、相続手続きをスムーズに進めるための重要な措置です。
しかし、生活資金の不足や公共料金の未払いなど、遺族にとって大きな影響を与える場合があります。
そのため、事前の対策や早期の手続きが求められます。
相続に関する手続きや銀行口座の凍結解除にお困りの方は、「相続オンライン相談センター」の専門家チームが丁寧にサポートいたします。
豊富な経験を持つプロフェッショナルが、必要書類の準備から手続き完了までサポートします。
詳しくは公式サイト(https://smallbiz.co.jp/souzoku/)をご覧ください。






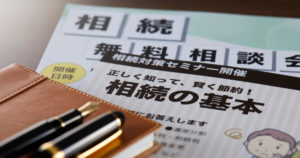
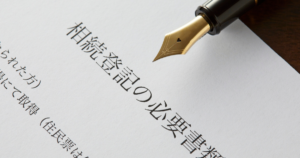

コメント